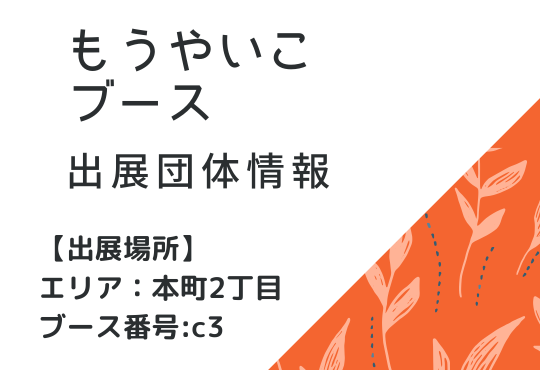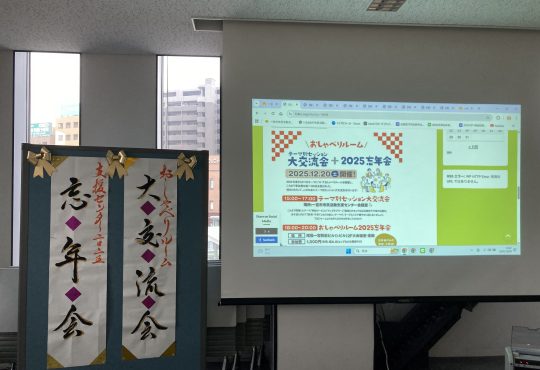【報告】市民活動のおしゃべりルーム~ヤングケアラー~vol.3
2025年10月26日(日)、市民活動支援センターにて「市民活動のおしゃべりルーム ヤングケアラーVol.3」を開催しました。
2024年8月25日、2025年3月9日に続き、3回目の開催です。
ヤングケアラー経験者や子ども関係の団体の方、町内会で活躍されている方など6名が参加され、ヤングケアラー経験者への質問と回答をベースに話題が展開。意見や感じたこと、できることは何かなど、さまざまな視点で話が盛り上がりました。
●こども家庭庁ホームページ「ヤングケアラーについて」(参考)
https://www.cfa.go.jp/policies/young-carer/

●ヤングケアラーについて参加者の思い
・ヤングケアラー本人は大変という自覚はない。
・「大丈夫?」と聞かれると「大丈夫です」と言うがそのまま受け取らないでほしい。
・ヤングケアラーの漫画でも「困っていない」と答えると書かれていた。
・コミュニティ最小単位の町内会が崩れつつあり危機感を感じている。
・多世代など人のつながりが大事。ヤングケアラーだけでなく防災にも。など
●ヤングケアラー経験者(複数名)のお話
(誰かに救ってもらった?)
・当時ヤングケアラーという意識はなく、助けてもらっていない。
・親の精神疾患で関わる医療や福祉の方が気にかけてくれた。
・同じような立場の人を探してくれて、話ができた。など
(ヤングケアラーという言葉について)
・当時は辛い状況が説明できず、苦労もよくわからなかった。
・「私はヤングケアラー」と若干ほっとしたが、その言葉に縛られるのは嫌だと思う。
・「ヤングケアラー」と言われても抵抗ない。まぁいいかなという感じ。など
(困ったこと)
・同年代と付き合いたいが、話題が合わず浅い友達関係になりがち。
・経験者としてオンラインで情報集めをしているが、経験者と繋がらない。など
(良かったこと)
・大変だけど生きていること。
・当時は必死だった。その経験から心理学の知識や生き抜く力を養えた。
・苦労はあったが、今は支援する側として何が必要か理解でき、立場や経験が生きている。
・医療や福祉の方に助けてもらったので、支援する側で役に立ちたい。など
●参加者のコメント
・ヤングケアラーの話をするところが少ない。
・かわいそうというレッテルを貼らず、一緒に考える。諦めてはいけない。
・知り合いだと話せない。初めましての方だからこそ話しやすかった。
・お話を聞きながら、「あの子そうだったかな」と思い出す時間だった。
・教育現場はキャッチしやすいと思った。
・経験者の方との日々話し合いで、諦めてはいけないと思っている。など
●今日のまとめ
・具体的な優しい問いかけを。例えば「しっかり眠れてる?(睡眠)」「ごはんはしっかり食べれてる?(食事)」「勉強する時間はある?」「遊ぶ時間はある?」など
・ヤングケアラー経験者の意見を聞いていくことは大事。
・困る前に知識ある人が寄り添いつなげていく。
・子どもらしく、自分らしく生きられるよう、環境のサポートをすることが大切。など

●参加者アンケート
1)今回のおしゃべりルームの評価 大変満足5名 満足1名
2)感想・意見
・今回もいろいろと聞くことができて、中身の濃い話しで視野が広がった。
・地域で活動している方との交流で新しい仲間、素晴らしい人たちに出会えた。
・回を重ねるごとに、ヤングケアラーの経験など自分のことを話しやすくなった。
・終了後もいろいろな話ができて有意義な時間だった。
・進行がフレンドリーで、協力し合えるのがセンターの良い所だと思った。
・経験者の話をじっくりと、感情の流れの喜びや悲しみを聞きたい。
・話し足りない。機会を増やしてほしい。など
●参加して(安田・今福)
第3回目もいろいろな立場や視点からの意見で盛り上がりました。ヤングケアラーと言っても背景はさまざまで、状況や価値観なども違います。
ヤングケアラー経験者からのお話をお聴きし、自分の価値観や思い込みで動かず、一人一人の言葉に耳を傾けて対話することの大切さを改めて感じました。
おしゃべりルーム終了後、センター閉館間際まで参加者同士で話が盛り上がっている様子を見て、主催したセンターとして、とても嬉しく思いました。
12月20日(土)に「おしゃべりルーム テーマ別セッション大交流会+2025忘年会」を予定しておりますので、ご関心のある方はぜひご参加ください!